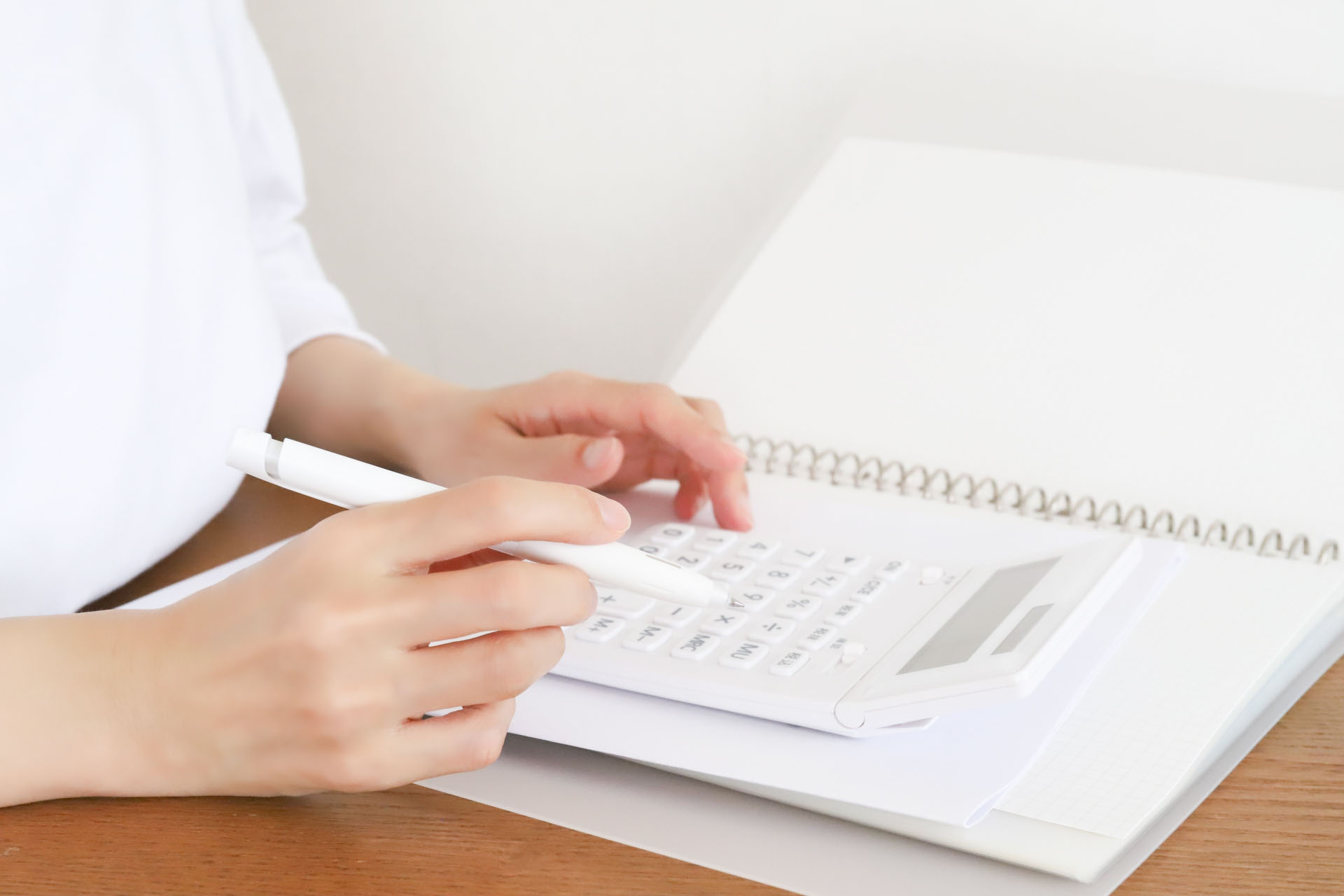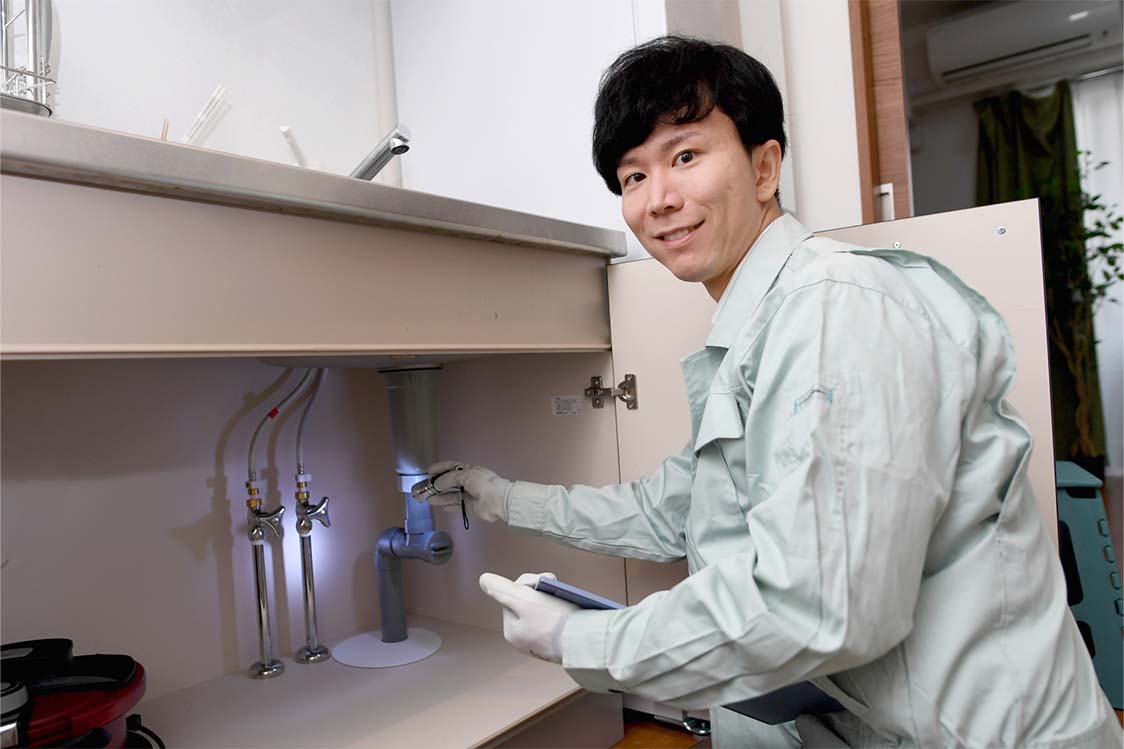雨水枡は新築でも水が溢れる!オーバーフローの原因と対処法を紹介
この記事では、雨水枡から水が溢れる問題についてまとめています。雨水を集水する役割を持つ雨水枡は、新築でも水が溢れるトラブルは起こりうるので注意が必要です。
記事を読むことで、主な原因やトラブルを解消するための掃除方法を把握できます。雨水を溢れさせない予防法も紹介するため、自宅の雨水枡で水が溢れて困っている方、仕組みを理解して予防策を取っておきたい方などは参考にしてください。
- 今週の
No.1 おすすめ優良業者!! -
詳細を見る

水廻り修理サポートセンター
【水道局指定工事店だから安心!】トイレの水漏れ・つまりなど水トラブルに最短30分で駆けつけます。もちろん〈出張費用・見積もり費用無料!〉大阪をはじめ関東/東海/近畿など幅広いエリアに対応。お困りの際はお気軽にご相談下さい!
この記事の目次
雨水枡から水が溢れる原因
雨水枡から水が溢れる原因には、主に以下のようなものがあります。
- オーバーフロー管でつまりが起きている
- オーバーフロー管が設置されていない
- 泥やゴミが蓄積している
- 大雨で雨水枡が処理しきれない
自身で対処できるものもあれば、業者に依頼しなければ解決しないものまでさまざまです。各原因の詳細について解説するため、トラブル時も冷静に対処できるようにしてください。
オーバーフロー管でつまりが起きている
雨水枡の中には、内部の水量が一定に達した場合に上部からの水漏れを防ぐ「オーバーフロー管」が側面に設置されているタイプがあります。このオーバーフロー管でつまりが起きていると、一定量を超えた雨水を正常に排水できず、水が溢れてしまうのです。
雨水枡のオーバーフロー管は、主に以下の理由でつまります。
- 雨水とともに流れ込んだ土砂や落ち葉が引っかかった
- 劣化・破損等で雨水が正常に流れない
- 地盤の変化や工事の影響で勾配がゆるくなり、スムーズに排水されない
つまりは自身でも解消できますが、手の届かない奥深くのつまりは水道修理業者を呼んで確実に対処してもらいましょう。
おすすめの水道修理業者は、こちらの記事でも紹介しています。
オーバーフロー管が設置されていない
雨水枡によっては、オーバーフロー管が設置されていないものがあります。たとえば、非浸透タイプでは雨水を下水に流すための排水管が取り付けられており、オーバーフロー管は付いていないものが多いです。
また、本来設置が必要な雨水枡でも、まれに施工ミスで取り付けられていないケースがあります。排水速度が追いつかない大雨の時は、オーバーフロー管がないと水が溢れやすいため要注意です。
泥やゴミが蓄積している
雨水枡には雨どいに付着した泥やゴミもまとめて流れ込んでくるため、これらが蓄積することで性能が低下して、水が溢れるトラブルにつながります。
また、蓋に穴が開いているタイプは、庭の土やゴミが穴から入り込んで蓄積する可能性もあります。掃除をしない限りは溜まり続けるため、定期的なメンテナンスで除去することが重要です。
大雨で雨水枡が処理しきれない
台風時の大雨やゲリラ豪雨など、雨水枡の処理能力を超えた雨量の場合も水が溢れます。この場合は自身での対処も難しく、改善したければ業者に依頼して雨水枡の数を増やす、雨水枡を広くするなど、工事を伴う対応を依頼するしか効果的な解決は望めません。
新築でも雨水枡が溢れる場合はオーバーフロー管を確認
家が新築で、住み始めて間もないのに雨水枡が溢れている場合、オーバーフロー管の状態を確認してみましょう。泥やゴミの蓄積によるつまりも新築では考えにくいため、オーバーフロー管が機能していない、または設置されていない可能性が高いです。
オーバーフローが正しく機能しているかどうかは、素人目では判断が付きづらいので水道修理業者やハウスメーカーに相談しましょう。
種類別!雨水枡の見分け方と掃除方法
雨水枡は大きく分けて、浸透タイプと非浸透タイプの2つに分けられます。呼称については、浸透タイプが「浸透枡」、非浸透タイプを「雨水枡」と呼び分けるケースもあります。
まずは自宅にある雨水枡がどちらの種類かを判別してから、作業にあたりましょう。雨水枡を掃除する場合は、どちらの種類でも以下の道具は揃えておいてください。
- スコップ(シャベル)、ひしゃく
- ゴム手袋
- バケツ
- ブラシ
見分け方と掃除方法を紹介します。
浸透・非浸透タイプの見分け方
浸透・非浸透タイプを見分ける基準のひとつが、蓋を開けた時の砂利や穴の有無です。浸透タイプは水を地面に浸透させる役割を持つため、水を流すために底や側面に穴が開いていたり、底に砂利が敷かれています。
一方の非浸透タイプは、底がコンクリートで覆われており、雨水を側溝や下水道に流すための配管が取り付けられています。まずは蓋を開けてみて、内部の構造を確認してみましょう。
浸透タイプの掃除方法
浸透タイプの雨水枡を掃除する際は、以下の手順を参考にしてください。
- 雨水枡の蓋を開ける
- 底に沈殿した泥・ゴミをスコップやひしゃくで取り出して、バケツに入れる
- 底に敷かれた砕石・浸水シートが見えるまで作業を繰り返す
- オーバーフロー管に泥や落ち葉がつまっている場合は取り除く
- 雨水枡の側面に付着した汚れをブラシで取り除く
- 雨水枡の蓋を閉める
基本的な雨水枡掃除は、蓋を開ける→底面に溜まった泥やゴミを除去する→蓋を元に戻すのが一連の流れです。加えてオーバーフロー管や枡の側面が汚れている場合は、ブラシ等を使って綺麗にしてください。
浸透枡の場合、底面には砕石や浸水シートが敷かれているため、底面の泥・ゴミを除去する時は破らないよう慎重な作業が求められます。除去した泥やゴミは、各自治体のルールに従って適切に処分しましょう。
非浸透タイプの掃除方法
非浸透タイプの雨水枡を掃除する際は、以下の手順を参考にしてください。
- 雨水枡の蓋を開ける
- 底に沈殿した泥・ゴミをスコップやひしゃくで取り出して、バケツに入れる
- 底に敷かれた砕石が見えるまで作業を繰り返す
- 雨水枡の側面に付着した汚れをブラシで取り除く
- 雨水枡の蓋を閉める
掃除の方法は、掃除の手順は浸透タイプとほぼ同じです。浸透タイプと異なり浸水シートは敷かれていませんが、底面にスコップなどを強く当てて傷つけないようにしてください。
また、沈殿物を除去する時は砕石まで取り出さないようにも注意しましょう。
雨水枡を掃除する時の注意点
雨水枡を掃除する時は、いくつか注意点があります。故障等で事態を悪化させないためにも、以下の注意点を踏まえて慎重に作業を進めてください。
浸透タイプは砂利を触らない
浸透タイプの雨水枡は、雨水を浸透させるため底に砂利が敷き詰められています。この場合、砂利を触らない・動かさないよう慎重に掃除を進めてください。
砂利の位置が大幅に変わると、従来の浸透機能が低下して効率よく雨水を吸収できなくなるおそれがあります。底に溜まる泥やゴミを取り除くのは問題ありませんが、ホースなどを用いて勢いよく洗浄する時は注意しましょう。
古い雨水枡は破損に気を付ける
古い雨水枡を掃除する場合、洗浄やブラシによって壁や配管が破損しないように気を付けましょう。劣化により耐久性が下がっているため、とくに高圧洗浄機を使うことはおすすめしません。
また、成分の強い薬剤を使用する場合も、古い雨水枡の構造が傷付くおそれがあるので注意してください。
集合住宅の場合は管理会社に連絡する
集合住宅の雨水枡は、駐車場やゴミ置き場周辺などの共用部に設置されています。そのため、水が溢れるトラブルなどを確認した場合は住民が掃除をせずに、必ず管理会社へ連絡してください。
管理会社は水まわりのトラブルがあった際、水道修理業者を手配して迅速に問題解決にあたってくれます。住民が自ら掃除をしたり業者を呼ぶと、かかる費用がすべて自己負担のケースもあるため要注意です。
雨水枡から水を溢れさせない予防法
雨水枡から水が溢れるトラブルは、ある程度の予防が可能です。そのためには、以下のような予防法をとりましょう。
- 年に1〜2回を目安に掃除する
- 蓋を交換する
- 非浸透タイプの場合は浸透タイプに切り替える
掃除以外の方法は業者依頼など手間もかかりますが、雨水枡から水が溢れるリスクを大幅に削減できます。
長く住み続ける住宅の場合、多少手間がかかっても、事前に対策をしておくことで快適な生活が続けられます。
それぞれの予防法を詳しく紹介するため、参考にしてください。
年に1〜2回を目安に掃除する
雨水を集める役割の雨水枡も、しばらく放置していると雨に混ざった泥やゴミが蓄積していきます。汚れの蓄積は排水を妨げてつまりの原因にもなるため、水を溢れさせないためには定期的な掃除が必要です。
汚水枡ほど汚れるスピードは速くないものの、年に1 〜2回を目安に掃除をするとよいでしょう。掃除のタイミングは、雨が多くなる梅雨前や、台風シーズンに入る前がおすすめです。
内部に溜まった汚れやゴミを除去する、配管を綺麗にするなど、雨水枡が本来の動きをできるようメンテナンスしてください。
蓋を交換する
雨水枡は大雨などの際、浸透や排水が追いつかずに水量で蓋が浮き上がるおそれもあります。
浮き上がりると内部の水も溢れるので、浸水対策・安全性強化のために鉄製の蓋に交換するのもおすすめです。
交換時は円形のサイズを正確に測る必要があり、自身で取り付けるのは困難です。蓋にも穴あき・穴なしタイプなど違いがあるため、業者に依頼して最適なものを取り付けてもらいましょう。
また、設置場所や状況によって適した蓋材質を選ぶようにしてください。
非浸透タイプの場合は浸透タイプに切り替える
自宅の雨水枡が非浸透タイプの場合、可能であれば浸透タイプに交換しましょう。浸透タイプは雨水を地中に浸み込ませて排水するため、非浸透タイプに比べて水が溢れるリスクも軽減されます。
雨水枡の交換は地面の掘削や基盤工事も必要になるため、業者に施工してもらうのがベストです。
雨水枡から水が溢れるトラブルは水道修理業者も対応可能
雨水枡から水が溢れる症状が解消しなければ、早急に水道修理業者へ修理を依頼しましょう。雨水枡や配管に関するトラブルは「水廻り修理サポートセンター」が対応可能です。
水まわりに関する悩みに幅広く対応、水道局指定工事店に認定された高い技術力で、トラブルを迅速に解決します。急なトラブルでも24時間365日、最短30分の駆けつけで安心です。
雨水枡の掃除や交換をはじめ、水まわり設備に関する相談はお気軽にご相談ください。
雨水枡が溢れるトラブルに関するよくある質問
- 雨水枡の交換費用の相場はいくらですか?
- 雨水枡から水が溢れるのを放置するデメリットは何ですか?
- 雨水枡は浸透・非浸透タイプのどちらがよいですか?